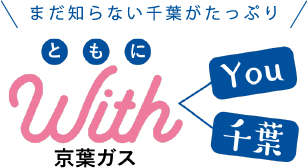今年も落花生収穫の季節がやってきました。落花生といえば千葉県を代表する特産品。じつは国内で消費される落花生は約90%を輸入に頼っており、国産のものはとても貴重! このたった1割しかない国産落花生の、なんと約80%が千葉県内で生産されているのです。今年は台風の影響もあって、県内の落花生も深刻な影響を受けました。しかし幸いにもなんとか被害を免れ、無事に収穫を迎えた地域もあります。自然災害を乗り越えながら、農家の方々が大切に、心をこめて育ててきた落花生。ぜひ、自分で収穫して、獲れたての生のおいしさを味わってみませんか。

千葉県の落花生は品種によって収穫時期が異なり、早いものでは9月から収穫できるものもあります。今回は、10月に収穫時期を迎える成田ゆめ牧場さんにお邪魔しました。
成田ゆめ牧場で落花生の栽培や管理を担当する大坪さんによると、牧場が落花生の栽培を始めたのはおよそ15年前とのこと。
「千葉県名産の落花生の収穫を、お客さまにぜひ体験していただきたいという思いから開始しました。当初は、植えたばかりの豆を鳥に食べられてしまうなどのトラブルもありたが、現在は防鳥ネットを張って鳥害を防止しています」と大坪さん。
成田ゆめ牧場で収穫できる落花生は「千葉半立(ちばはんだち)」という品種。甘みとコクがあるのが特徴で、千葉県奨励品種のひとつとなっています。今年は9月の台風にも負けず、牧場では昨年よりも実りがいい状態とのことです。

成田ゆめ牧場の大坪さんに聞きました。
落花生ってどうやって育つの?
5月中旬ごろに種を植えますが、じつはその種はいわゆる「ピーナッツ」そのものなんです。落花生の殻を取り除いた中身を毎年保存しておき、翌年畑に植えて、肥料を与えて育てます。
収穫のコツを教えて!

葉や茎が黄色みを帯びてきて、下葉が枯れてきたら収穫のタイミングです。さやがかたくなっているのは、カルシウムをじゅうぶんに吸収しておいしくなっている証拠。掘り起こした落花生を10日ほど天日干しすると、完成です!
じょうずな保存方法は?
天日干しでしっかり乾燥させておけばカビも防げます。通気性がよく涼しいところに保管しておき、翌年その実を種にして栽培するのもいいですね。
おいしい食べ方を教えてください
新鮮な落花生は、ゆでてよし、煎ってよし! 両方のおいしさを味わってみてください。
ぜひ試していただきたいのはゆで落花生。落花生を塩水でゆでるだけととっても簡単ですが、ほくほくとした格別のおいしさが味わえます。生の落花生200gに対し、塩水500ml(塩10gを入れた水500ml)目安。強火で50分ほどゆでます。ゆで終わったら火をとめ、そのままゆで汁が冷めるまで浸しておきます。こうすると塩味がしみ込んで甘みも出てきます。
煎りの場合は、さやのままフライパンで約30分から煎りし、ピーナッツの香ばしい香りがしてきたらできあがりです。煎るときに塩を少々加えるとおいしくなります。
成田ゆめ牧場での落花生収穫体験は、家族連れを中心に毎年大好評とのこと。「落花生の育ち方を初めて知った」「掘るのが楽しい!」といった子どもたちの声が聞かれるそう。収穫体験は、子どもたちがふるさとの恵みを知り、受け継いでいくという大きな役割も担っているようです。
千葉の落花生にもっと愛着を持ってほしいと牧場が始めたのが「オーナーイベント」。落花生のオーナーとなった家族は、春の植えつけと秋の収穫を両方楽しめます。お世話はスタッフが行うので、収穫を待つだけ。「落花生を育ててみたいけど家にお庭や畑がない」といった方々に好評とのことです。
国内生産量第1位を誇る千葉県の落花生ですが、県内でも年々生産量が減っており、ピーク時の昭和30年代後半の約6万トンに比べ、現在は約5分の1に。千葉県産落花生はそのおいしさで、全国の消費者から高い支持を得ています。千葉の落花生の伝統を守るためにも、私たちは食べ続けることで応援していきたいですね。今年はぜひ、家族でふるさとの旬の恵みを味わってみてください!
【成田ゆめ牧場】
落花生掘りは牧場内の第一ゆめ牧場農園で10月いっぱい開催しており、3株600円で収穫・持ち帰り可能。別途、成田ゆめ牧場の入園料が必要です。詳しくはホームページを。
千葉県成田市名木730-3
☎0476-96-1001
※2019年10月時点の内容です。
取材・文/植木淳子